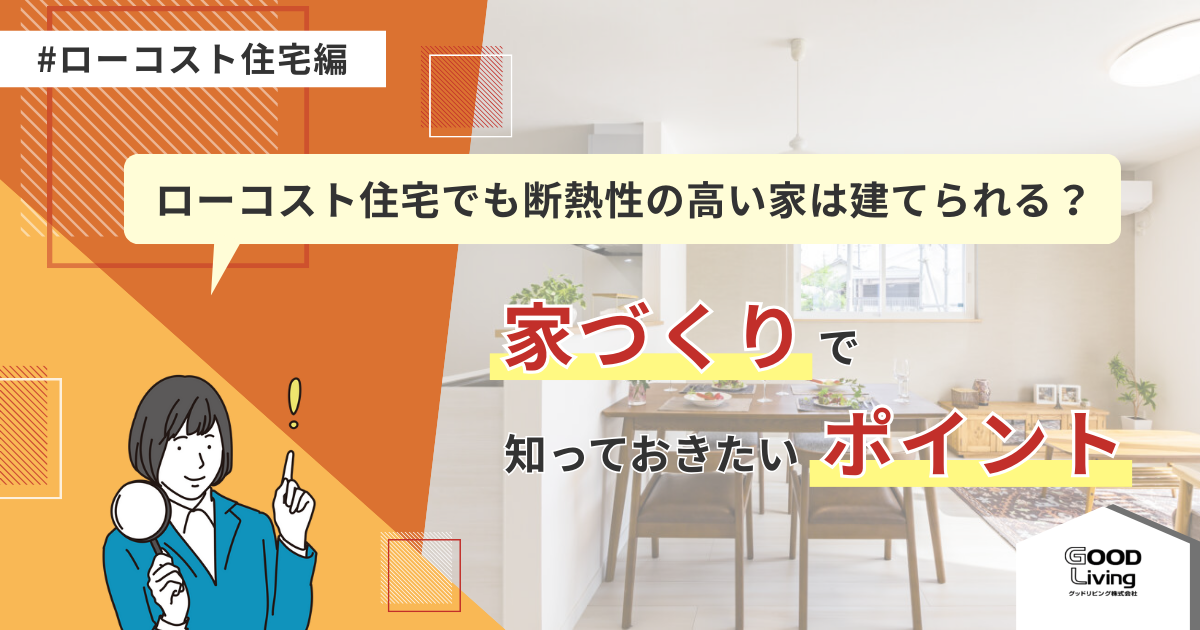COLUMN コラム
断熱性の高い家は、年中快適に過ごせることや、冷暖房費を抑えられるなど経済的なメリットなどから、近年では断熱性を重視した家づくりが主流となっています。
一方で、ローコスト住宅は価格の手頃さから、「断熱性能は大丈夫なの?」と心配する声もあります。
しかし、安心してください。実際には、ローコスト住宅でも、さまざまな工夫によってコストを抑えながら、断熱性の高い家が実現できます。
そこで今回は、断熱性能を測る基準や、断熱材やサッシの種類・特徴について詳しく解説します。
また、コストを抑えつつも高断熱な家を建てるポイントをご紹介しますので、ぜひ今後にお役立てください。
断熱性の高い家とは

こちらの事例:ナチュラルテイストのお家
断熱性の高い家とは、外気の影響を受けにくく、家の中の温度を一定に保ちやすい家のことをいいます。夏は外の暑さを防ぎ、冬は室内の暖かさを逃がしにくいため、1年中快適に過ごせるのが特徴です。また、冷暖房に頼りすぎずに済むため、省エネ効果も期待できます。
ローコスト住宅でも断熱性を意識すれば、こうした快適な住まいが目指せます。まずは家の断熱性をどのように判断するのかを知っておきましょう。
断熱性の高さを判断する基準
断熱性の高さは、いくつかの基準によって数値化されています。代表的なものに、「断熱等級(断熱等性能等級)」「UA値(外皮平均還流率)」「HEAT20」があり、これらを参考にすることで、家の断熱性を比較できます。
・断熱等級(断熱等性能等級)
断熱等級とは、住宅の断熱性能を数値化してランク付けしたものです。
主に、「建物からの熱の逃げやすさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を判断します。
最高ランクは「等級7」で、数字が大きくなるほど、断熱性能が高いことを意味します。
【断熱等級の特徴】
| 等級 | UA値の目安(6地域の場合※) | 室温維持目標 | 断熱性能の特徴 |
| 等級4 | ≦0.87 | 概ね8℃を下回らない | 最低限の断熱性能。2013年の省エネ基準に相当 |
| 等級5 | ≦0.6 | 概ね10℃を下回らない | 長期優良住宅やZEH基準の断熱性能 |
| 等級6 | ≦0.46 | 概ね13℃を下回らない | 高断熱で快適性が高い。HEAT20 G2に相当 |
| 等級7 | ≦0.26 | 概ね15℃を下回らない | 最高レベルの断熱性能。HEAT20 G3に相当 |
※地域によってUA値(外皮平均熱貫流率)の基準は異なります。上記は6地域(例:愛知・東京など)の目安です。
長期優良認定住宅や、ZEH住宅は、等級5以上が求められます。
また、2030年以降に建築される新築住宅では、断熱等級5以上が義務付けられる予定です。
・UA(ユー・エー)値
UA(ユー・エー)値とは、「外皮平均熱貫流率」のことで、「建物からの熱の逃げやすさ」を数値化したものです。
数値が小さいほど断熱性能が高いことを示し、前述した断熱等級にも使用されています。
また、北海道のような寒冷地ではより小さなUA値が求められるなど、地域によって基準が異なります。
・HEAT20(ヒートニジュウ)
HEAT20(ヒートニジュウ)は、「冬でも暖かく健康的に過ごせる住宅」の実現を目指して、国の基準よりもワンランク上の断熱性能を目安としたガイドラインです。
G1・G2・G3と3段階のレベルがあり、数字が大きくなるほど断熱性が高いことを示します。
【HEAT20(ヒートニジュウ)の特徴】
| グレード | 対応する断熱等級の目安 | UA値(6地域の場合※) | 特徴 |
| G1 | 等級5相当 | ≦0.56 | 断熱強化の入門レベル。快適性や省エネが向上。室温が冬でも10℃を下回りにくくなる断熱等級4(省エネ基準)から暖房負荷削減率は約4 割削減できる※ |
| G2 | 等級6相当 | ≦0.46 | 快適性・健康面で大きな効果。ヒートショック対策にも有効。室温が冬でも13℃を下回りにくくなる断熱等級4(省エネ基準)から暖房負荷削減率は約5.5割削減できる※ |
| G3 | 等級7相当 | ≦0.26 | 最高クラスの断熱性能。暖冷房の負担がほぼ不要に近い室温が冬でも15℃を下回りにくくなる断熱等級4(省エネ基準)から暖房負荷削減率は約7.5割削減できる※ |
※地域によってUA値の基準は異なります。上記は6地域(例:愛知・東京など)の目安です。
断熱性の高い家のメリット・デメリット

こちらの事例:シンプルで暮らしやすいお家
断熱性の高い家には、快適性や省エネ性など多くのメリットがありますが、コストや換気の面でのデメリットもあります。
納得のいく家づくりのためにも、メリットだけでなく、デメリットもしっかり理解しておきましょう。
断熱性の高い家のメリット
まずは断熱性の高い家のメリットについて解説します。
・夏は涼しく、冬は暖かい
最も大きなメリットは、季節を問わず年中快適に過ごせる点です。
断熱性の高い家は、外の暑さや寒さを室内に伝えにくいため、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。
例えば、断熱等級5の家では、暖房期の最低気温はおおむね10℃(地域区分3〜7の場合)を下回らない程度とされています。
室内が凍えるほど寒くなることは少ないため、例えば、小さな子どもがいるご家庭など入浴時の着替えに多少時間がかかってしまっても、安心です。
・光熱費を抑えられる
断熱性の高い家のもう一つのメリットは、年間の電気代が抑えられるという点です。
外壁や屋根、床、窓などに断熱材がしっかり入っていると、外の暑さや寒さが家の中に伝わりにくくなります。
さらに、室内の暖かさや涼しさも外に逃げにくくなるため、冷暖房に使うエネルギー量が減り、光熱費が削減できます。
実際にどれくらい削減できるか、「エネルギー消費性能計算プログラム住宅版」を用いて年間の消費電力量を算出し、断熱等級別に電気料金を比較してみました。
【シミュレーション条件】
- 地域:6地域
- 床面積:120.08㎡
- 外皮面積:307.51㎡
- 冷暖房:居室のみエアコン使用
- 給湯:ガス従来型給湯器
- 照明:すべてLED照明
- 電気会社:中部電力ミライズ「おとくプラン」従量電灯B・契約容量60A
| 断熱等級 | UA値 | 設計二次エネルギー消費量 | 年間電気代 ※基本料金含む | 等級4との差額 |
| 等級4 | 0.87 | 4,821kwh | 148,164円 | – |
| 等級5 | 0.6 | 4,491kwh | 138,699円 | 9,465円 |
| 等級6 | 0.46 | 4,221kwh | 131,485円 | 16,679円 |
| 等級7 | 0.26 | 4,026kwh | 126,532円 | 21,632円 |
このように、等級が高いほど年間の光熱費が安くなることがわかります。しかし、あくまでもシミュレーションであり、実際に契約する電気料金プランや立地や建物条件、生活スタイルなどによって差があるため、参考程度にしてください。
・家族の健康を守れる
断熱性の低い家では、冬に室内と外気の温度差が大きくなり、窓や壁に結露が発生しやすいのが問題視されていました。
この結露が原因でカビが繁殖すると、アレルギーや喘息などの健康被害を及ぼすこともあります。
しかし、高断熱の住宅では室内の温度差が少なくなるため、結露が起きにくく、カビの発生も抑えられます。
また、断熱性能の高い家は、家全体の温度差が少ないため、ヒートショックなどのリスクも防げる効果も。
ヒートショックとは、寒暖差による急激な血圧変化が原因で起こる健康被害のことで、とくに冬場、暖かいリビングから寒い浴室やトイレへ移動したときに起こりやすいとされています。
高齢の家族と同居する場合や、将来を見据えた家づくりを考えることも大切なポイントです。
断熱性の高い家のデメリット
快適性や省エネ性が高い一方で、断熱性を高めるためには初期費用がかかったり、適切な換気が必要になるといった注意点もあります。
・初期費用が掛かる
高性能な断熱材や複層ガラス、断熱サッシなどを採用すると、建築費用が上がることがあります。
とくにローコスト住宅では、もともとの性能がどの程度かにもよりますが、価格とのバランスをどう取るかが悩ましいところでしょう。
ただし、初期費用が多少増えても、光熱費の節約や快適性の向上など、長い目で見ればメリットは大きいといえます。
先述したように、「エネルギー消費性能計算プログラム住宅版」を用いて算出した年間の消費電力量でシミュレーションした結果でも、光熱費は等級が高いほど削減できると考えられます。
その他にも、サッシメーカーのYKKapが公開している資料も参考にすると、断熱等級に応じた年間の冷暖房費は、断熱等級5の場合は約17,289円、断熱等級6の場合は約19,977円、断熱等級7の場合は約35,415円お得になることがわかります(※断熱等級4と比較した場合)。
つまり、初期費用で100万円かかったとしても、ローンを支払うまでに一部分を回収できる場合もあるので、将来の生活コストも含めて検討することは賢明な選択といえます。
参考:断熱等級5・6・7それぞれのおすすめ2024.10(YKKap)
・適切な換気が必要
断熱性の高い家は、気密性も高める必要があるため、空気がこもりやすくなるため、計画的な換気はとても重要です。
24時間換気システムなどを活用し、常に新鮮な空気を取り込む必要があります。
また、換気が不十分だと、湿気がたまり結露やカビが発生する場合もあります。
断熱と気密、そして換気のバランスをしっかり考えることが、健康で快適な家づくりのカギになります。
ローコスト住宅で断熱性の高い家を建てるポイント

こちらの事例:廊下のない平屋
ローコスト住宅で断熱性の高い家を建てるには、断熱性能を大きく左右する「断熱材」と「窓」で何を選ぶかが非常に重要となります。
どちらも種類や性能に幅があり、費用をかけずに高断熱を目指すには、特徴を理解したうえで賢く選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの特徴を紹介し、さらに「押さえておきたいポイント」も含めて5つご紹介します。
①断熱材
断熱材は、住宅の壁や床、天井などに使用され、外気の影響を受けにくくする役割を持ちます。ローコスト住宅においても、断熱材の選び方や使い方を工夫することで、断熱性をしっかり確保することが可能です。断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれ性能や価格に違いがあります。
・断熱材の種類
木造戸建て住宅でよく使われる断熱材は以下の通りです。
| 断熱材の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| グラスウール | ガラス繊維でできたふわふわの素材 | ・安価で入手しやすい ・防音性が高い | ・湿気に弱い ・丁寧な施工が必要 |
| ロックウール | 岩石を繊維状にした素材 | ・防音性・耐火性が高い | ・湿気に弱い |
| 押出法ポリスチレンフォーム | 発泡スチロール状のボードタイプ | ・水に強い ・施工が簡単 | ・ボード同士の継ぎ目に隙間ができやすい ・燃焼すると有毒ガスが発生する |
| セルロースファイバー | 古紙を使った自然素材の吹込み断熱材 | ・調湿・防音性に優れる ・エコで環境にやさしい | ・施工に技術が必要 |
| 発泡ウレタン(吹付) | 現場で発泡させるスプレータイプの断熱材 | ・気密・断熱性が高い ・隙間なく施工可能 | ・解体・リフォームしにくい |
| フェノールフォーム(ネオマフォーム) | フェノール樹脂を発泡させた硬質断熱材 | ・断熱性・耐火性は非常に高い ・薄くても断熱性を確保できる | ・施工に技術が必要 |
ローコスト住宅で断熱性の高い家(断熱等級5以上)は、発泡ウレタンやグラスウールを使用していることが多いです。
また、トップクラスの断熱性能をもつ、フェノールフォーム(ネオマフォーム)を採用している会社もあります。
気密性や断熱性を考慮すると、発泡ウレタンやフェノールフォームが最適ですが、価格とのバランスを考えるなら、グラスウールもおすすめです。
・断熱材の厚み
断熱材の種類だけでなく、厚みも断熱性能に大きく関わります。
なぜなら、厚みがあるほど熱の出入りを抑えることができ、室内の温度を安定させやすくなるためです。
ただし、厚くするほど材料費や施工費がかかるため、必要な断熱性能に応じた厚みを選ぶことが大切です。
②窓
住宅の中で最も熱の出入りが大きい場所が「窓」です。
窓は、壁や天井の断熱材以上に、窓室内の快適性や省エネに大きく関わります。
もし、標準仕様の断熱性能が不十分であっても、窓ガラスやサッシの性能を見直すことで断熱性を大きく高められます。
・ガラス
窓に使われるガラスには、単板ガラス、複層ガラス、Low-E複層ガラスなどがあります。その特徴を、以下に特徴をまとめました。
【窓ガラスの種類と特徴】
| ガラスの種類 | 構造 | 断熱性 | 遮熱・日射調整機能 | 価格帯 | 主な用途・特徴 |
| 単板ガラス(1枚ガラス) | ガラス1枚のみ | 低い | なし | 安価 | ・最も安価 ・断熱性は低く、結露しやすい |
| 複層ガラス(ペアガラス) | 2枚のガラス+中空層 | やや高い | 一部あり | やや高い | ・現代の標準的ガラス ・単板ガラスに比べ、断熱・防音性がアップ |
| Low-E複層ガラス | 片側にLow-E(金属膜)+中空層 | 高い | 高い | 中〜高 | ・遮熱・断熱を両立 ・省エネ住宅に向いている |
| トリプルガラス | 3枚ガラス+2つの中空層+Low-E膜など | かなり高い | 非常に高い | 高価 | ・高断熱・高気密住宅向け ・寒冷地やG2以上に推奨 |
単板ガラスは1枚のガラスで構成されており、最も安価ですが断熱性は低めです。
複層ガラス(二重ガラス)は、2枚のガラスの間に空気層をつくることで、単板に比べて断熱性が高くなります。
さらに、Low-E複層ガラスでは、ガラスの内側に特殊な金属膜(Low-E膜)をコーティングし、遮熱効果も高めたものです。
Low-E膜は、夏の暑さを防ぐ「遮熱タイプ」と、冬の熱を逃がさない「断熱タイプ」があり、地域や季節に応じて使い分けられます。
標準的な断熱性なら複層ガラスで充分ですが、省エネ性や断熱性を高めたいなら、Low-E複層ガラスやトリプルガラスのほうが、より効果を発揮できます。
・サッシ
サッシ(窓枠)の素材も、断熱性に大きく関わるポイントです。戸建て住宅で主に使われるのは、以下の3種類です。
- アルミサッシ:軽量で安価だが、熱を通しやすく、結露しやすい
- 樹脂サッシ:価格は高いが、熱を通しにくく、断熱性が高いのが特徴。
- アルミ樹脂複合サッシ:アルミと樹脂を組み合わせたもので、価格と性能のバランスに優れている
これらの断熱性の高いガラスやサッシを組み合わせることで、家の断熱性能を向上できます。
また、窓の数やサイズを工夫しながら、少ない投資で効果を出すことも可能です。
③気密性
断熱性を高めるには、同時に気密性にも注目することも大切です。
なぜなら、いくら高性能な断熱材を使っても、すき間から空気が漏れてしまうと、その効果が半減してしまうからです。
気密性を高めるためには、施工時の丁寧な処理が重要となります。
コンセントまわりや窓枠のすき間、天井や床との接合部など、気密テープや気密シートを活用しながら隙間をなくすことで、気密性を高めることが可能です。
④間取り
省エネ性や快適性を重視して、断熱材や窓を性能の高いものを選ぶことは効果的ですが、どうしても費用はかかってしまいます。
しかし、間取りを工夫すれば、コストを抑えつつ、高い省エネ性や快適性を実現できます。
・コンパクトでシンプルな間取り
シンプルな四角い形状の家は、熱が逃げにくく断熱性能を確保しやすくなります。
また、外壁面積が少なくなることで、使用する断熱材の量も抑えられ、コスト削減にもつながります。
特に平屋は2階がなく、上下の空気移動が少ないため、より効果を発揮できます。
・部屋が集約している間取り
LDKと水まわり、寝室などの生活空間を集約している間取りは、1台のエアコンでも効率良く室温を管理できます。
また、各部屋の行き来もスムーズになるため、家事効率が向上されたり、家族とのコミュニケーションが増えたりするメリットもあります。
⑤施工が丁寧な会社
どんなに高性能な断熱材や窓を選んでも、施工が雑だと本来の性能を発揮できません。
前述したように、高い断熱性には気密性を確保することも重要です。
ローコスト住宅では、コストを抑えながらも丁寧な施工をしてくれる信頼できる工務店やハウスメーカー選びが重要です。
断熱材と構造の接合部や配管周りなど、細かい部分まで丁寧に施工されているかなど、施工中の現場を確認したり、実績や口コミを参考にしたりすることで、確かな施工技術を持つ会社を選ぶようにしましょう
まとめ
今回の記事では、断熱性能を測る基準や、断熱材やサッシの種類・特徴、コストを抑えつつも高断熱な家を建てるポイントについて解説しました。
断熱性を高めることは、年中過ごしやすい住まいが実現できるだけでなく、高い省エネ性や家族の健康維持にもつながります。
もちろん、今回ご紹介したように、ローコスト住宅でも様々な対策により、断熱性能の高い家が建てられますので、ぜひご紹介した内容もぜひ参考にしてください。
グッドリビングでは、「いい家を、より安く」を合言葉に、高性能な家を手が届く価格で提供してきました。
断熱等級6(UA値0.46W/㎡・K)という高い断熱性が標準仕様となっています。さらにHEAT20 G2グレードを取得。
冬でもエアコン1台で快適に過ごせる断熱性能が実現可能です。
土地探しや家づくりのご相談から、モデルハウスの見学予約など随時受付中です。
グッドリビングの注文住宅については、ぜひ以下のHPからお問い合わせください。
▼ホームページはこちら▼

監修者情報
グッドリビング広報部

累計15000棟以上の実績があるグッドリビングが、WEBサイト上の情報をまとめただけの簡易的な記事でなく、実際のお客様とのコミュニケーションの中である悩みや疑問をテーマにしています。真剣に新築注文住宅を検討している読者に役立つ、価値ある中身の濃い情報をお届けしています。