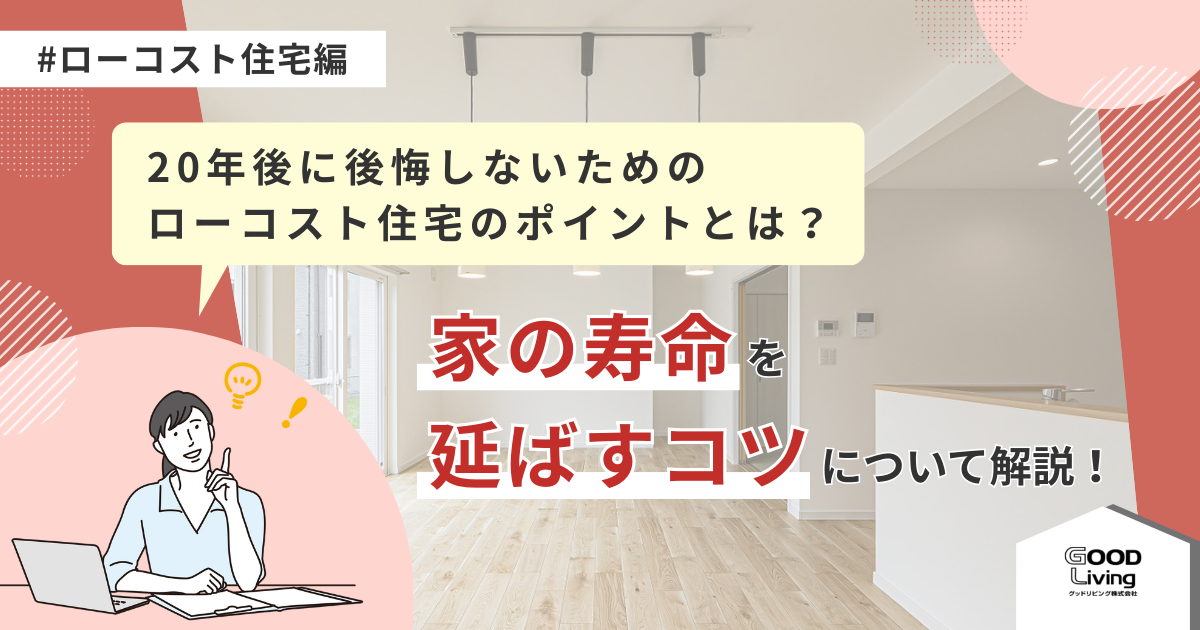COLUMN コラム
返済負担を軽くできるローコスト住宅ですが、価格が安い分、「20年後も安心して暮らせるのか」という不安もある人もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、そういった不安を解消するために、ローコスト住宅の価格が安い理由や、実際に住んでいる人の声を集めてご紹介します!
また、後悔しないためにできる対策や、20年先を見越した家づくりのポイントついても解説します。
コストを抑えながら、長く安心して住める家づくりのヒントとして、ぜひ役立ててくださいね。
ローコスト住宅が安い理由とは?

こちらの事例:家事に集中しやすい半独立キッチン | グッドリビング株式会社
ローコスト住宅は価格が安いため、「使用する資材の品質を落としているのではないか」というイメージがあるかもしれませんが、材料の品質はハウスメーカーによって大きくは変わりません。
なぜなら、新築の家を建てるには、建築基準法に適合する必要があるからです。
そのため、ローコスト住宅であっても、耐震性や防火基準などの安全性や、断熱性能など、国が定める基準を必ず満たして建てられています。
では、なぜローコスト住宅が実現できるのかというと、間取りや設備を規格化し、材料を一括仕入れすることで単価を抑えているためです。
また、施工の効率化による人件費の削減や、モデルハウスではなく、ネット中心の営業によって広告費を抑えている場合もあります。
実際にローコスト住宅を建てた人はどう思ってる?

実際に、ローコスト住宅で暮らしている人がどう思っているのでしょうか。SNSに挙げられている声をまとめてみました。良かった点、悪かった点として多く見られたのは次の通りです。
| ローコスト住宅で良かった点 | ・コスパが良く、返済負担を減らした分、投資などの資産形成に回せる、教育費や老後資金に使える。 ・地元のことを良く知っていて安心。 ・断熱性も問題なく快適に過ごせている。 ・最高レベルの耐震等級3が取得でき、地震も安心。 ・打ち合わせ決めることは、SNSなどで情報を集めれば分かることが多く、スムーズだった(そこまでこだわらずに早く家を建てたい人はおすすめ)。 ・結局は営業担当者との相性が大事。 |
| ローコスト住宅で後悔している点 | ・標準仕様のままだとコンセントの数や収納が足りない。 ・施工精度が雑に感じた。 ・選べる設備が少なく、間取りも制限されたため、後々にリフォームが必要になった。 ・大きな地震で倒壊は免れても、ダメージは受けるので心配。 ・ローコスト住宅といっても標準仕様の内容がさまざまであり、見極めるのが難しい。 |
ローコスト住宅で家を建てた人はコストパフォーマンスの良さに満足している一方で、設備や間取りに制限があることをデメリットとして感じる人もいるようです。
また、メーカーが謳う「ローコスト住宅」の範囲がさまざまであり、比較するのが難しいという声もありました。
ローコスト住宅で、家の寿命を延ばすために必要な3つの対策【構造】

こちらの事例:解放感のある南向きの家 | グッドリビング株式会社
国が定めた法定耐用年数によると、木造住宅は22年が目安となっています。
つまり、建築基準をクリアしたローコスト住宅なら、20年後も十分に住み続けることが可能です。
さらに、環境に適した対策や、定期的なメンテナンスをしておけば、20年以降も住み続けられます。
具体的にはどのようなことをすればよいのでしょうか。ここではまず、環境に適した構造部分の対策を3つご紹介します。
対策①地盤と構造の補強
家の安全性と耐久性を確保するためには、まず、家の地盤が強固な土台となりえるかどうかを知る必要があります。
どんなにしっかりした家を建てたとしても、地盤が弱ければ、家全体が傾いたり、ひび割れたりといった深刻な問題が発生するかもしれません。
地盤調査を行い、必要に応じて改良工事を行えば、何十年も安心して住み続けることが可能です。
また、地震が頻発する地域や、震度6以上の大型地震が起こると予想される地域では、耐震補強工事を行うこともおすすめします。
耐震工事には3種類あり、耐力壁の追加や接合部を強化し横揺れを抑える「耐震工法」、構造内に制震タンパーを設置し、地震の揺れを抑える「制震工法」、建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを逃がす「免震工法」があります。
戸建て住宅では「耐震」が一般的ですが、最近は「制震」と組み合わせて、一度の地震でも極力ダメージを抑えられる家が増えてきています。
長く安心して住める家には、強い地盤や構造が必要不可欠ですが、地盤改良工事や耐震工事によって、追加費用がかかる場合もあります。
地盤に問題はないか、もしくは標準の耐震性能や採用している工法は何かを、施工業者に事前に確認しておくと安心です。
費用の目途が立てば、大きく予算を超えてしまうことは防げるでしょう。
対策②防虫・防腐対策
木造住宅は、防虫対策や防腐対策をしっかりしておくことも必要です。
例えば、シロアリが発生すると、家の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。
シロアリは木材の内部から食べていくため、外見上は問題がないように見えても、内部は空洞になっていることがあります。
したがって、被害に気づいたときには、すでにかなり進行しているケースも多く、場合によっては床が抜けたり、家が傾いてきたりすることも。
そのため、定期的な防蟻処理や専門業者による検査・対策が必要です。
また、日本の夏は高温多湿になるため、床下や屋根裏、壁内部は湿気が溜まりやすく、木材の腐敗やカビの発生により、構造が痛む原因となります。
これらを予防するには断熱材や防湿シートの設置が効果的です。
こうした対策が取られているかを施工業者に確認するとともに、被害が発生した場合の保障内容についても確認しておくと安心です。
対策③適切な換気と断熱
先述したように、湿気やカビは、家の劣化の原因となります。
また、これらは家の構造だけでなく、住む人の健康を損ねる可能性もあります。
国内では24時間換気システムの導入が義務付けられており、換気・吸気ができる設備を必ず設置するようになっています。
この換気システムを適切に使用することや、さらに、室内の対角線上に窓を設けて空気の通りを良くし、効率的に換気を行うこと、湿気やカビはある程度防げます。
また、家を長持ちさせるには、断熱性能を高めることも効果的です。
断熱性の高い家は外気温の影響を受けにくいため、結露やカビの発生だけでなく、冷暖房費も抑えられます。
断熱性を高めるためには、使用する断熱材の種類や、気密・断熱効果のあるサッシを使用します。
検討している施工業者があれば、事前に確認しておきましょう。
20年先を見越した家づくりのポイント【外観・間取り】

こちらの事例:将来を見据えた1.5階建ての家 | グッドリビング株式会社
家づくりでは、目先のイメージだけでなく、10年、20年後の暮らしも視野に入れて考えることも大切です。ここでは、家の外観や間取りに焦点をあて、3つのポイントをご紹介します。
コンセントと収納は妥協しない
ローコスト住宅で注文住宅を建てる際には、間取りや住宅設備、電気設備など、ある程度決まっていることが多いです。
費用を抑えるためには、規格化された中で家づくりを進めることをおすすめしますが、提案された間取りや設備が、必ずしもどのご家庭に合うとは限りません。
とくにコンセントや収納は、住み始めてから後悔しやすいポイントでもあり、妥協しないほうが良いでしょう。
コンセント設置の目安と家電製品の使用例
コンセントは延長コードやタコ足配線でも増やせますが、どうしても見た目が悪くなってしまいます。
また、火災の原因にもなりますので、できるだけ妥協せず、必要な箇所に設置するのがおすすめです。
コンセントは間取り図ができた段階で、生活をシミュレーションしながら、どこにどのような家電を使用するかをイメージしてみましょう。
【家電の使用例】
- キッチンまわり・・・電子レンジ、炊飯器、電気ケトル・ポット、トースター、コーヒーメーカー、フードプロセッサー・ミキサー、ホームベーカリー、電気クッカーなど
- 洗面所・・・ドライヤー、ヘアアイロン、電気シェーバー、電気歯ブラシ、美顔器、小型ヒーターなど
- テレビ周辺・・・テレビ本体、DVDレコーダー、ゲーム機、スピーカー、Wi-Fiルーター・モデム、間接照明など
- スタディスペース、デスクワークスペース・・・パソコン、スマートフォン・タブレットの充電(兄弟がいれば人数分あると便利)、デスクライト、プリンター、Wi-Fiルーター・モデム、加湿器など
- ベッドの枕元・・・スマートフォン・タブレットの充電、照明、アロマディフューザー、加湿器、電動ベッドなど
収納の目安
理想的な収納率は、床面積に対して10〜13%と言われています。
30坪の一戸建ての場合、約3〜4坪(約6〜8畳分)程度を目安に収納スペースを設けると良いでしょう。
寝室にファミリークローゼット、キッチンにパントリー、玄関に土間収納など、使いやすい位置に分散して配置すると満足度の高い間取りが作れます。
収納スペースの確保が難しい場合は、階段下や屋根裏などを有効活用するのも方法の一つです。
外壁と屋根はメンテナンスしやすいものを選ぶ
家の外観の要素である外壁や屋根は、10〜15年おきに塗装や補修が必要になることが多く、素材によってもメンテナンスの頻度や費用は大きく異なります。
| 素材 | メンテナンス時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 窯業系サイディング | 約10年ごと | ・種類が豊富で外壁材としては一般的。 ・約10年ごとに塗り替えが必要。 |
| ガルバリウム鋼板 | 約15~20年ごと | ・サビに強く、軽量で長寿命。 ・塗装メンテナンスを行う。 |
| タイル | 約30~40年ごと | ・色あせ・劣化が非常に少なく、メンテナンスはほぼ不要(目地補修は必要)。 |
| スレート屋根 | 約10年ごと | ・軽量だが劣化しやすい。 ・塗装メンテナンスを行う。 |
最も耐用年数が高いタイルは、メンテナンスがほぼ必要ないのがメリットですが、費用は他の素材に比べて高額です。
コストパフォーマンスを重視するなら、汚れにくく色あせにも強い、ガルバリウム鋼板を検討してみると良いでしょう。
シンプルでシャープなデザインが作りやすく、モダンな外観がお好みの方にはおすすめです。
窯業系サイディングは、メンテナンス頻度が高い傾向にありますが、紫外線による色あせや、汚れ・傷に強いコーディングを施したものもあり、メンテナンス頻度を延ばすことも可能です。
外壁や屋根は劣化が進むと、見た目だけでなく、雨漏りなどの原因にもつながる事例もあります。
ローコスト住宅では、屋根や外壁の種類がある程度決められていることが多いので、メンテナンスのしやすさや、耐久性に優れたものを選択できるか確認してみると良いでしょう。
ライフステージの変化に対応できる間取り
20年も暮らしていれば、家族の暮らし方にも、さまざまな変化が訪れることでしょう。
例えば子供がいる家庭の場合、子供中心の子育て期があり、やがて夫婦二人の生活になり、さらに、自宅で親の介護をする必要があるかもしれません。
子供がいる間は子ども部屋などが必要ですが、子供が巣立った後は、子供部屋の使い道に困ってしまうかもしれません。
注文住宅で家を建てるなら、こうした生活スタイルの変化にも対応できるような、柔軟な間取りを意識することも大切です。
最近では子ども部屋を4.5畳ほどのコンパクトな広さにして、将来は収納スペースやワークスペースに充てる間取りも人気です。近年高まっている健康志向により、トレーニングスペースとして活用される方もいます。
ぜひ、20年先の家族の暮らしを想像しながら、理想の住まいをプランニングしてみましょう。
ローコスト住宅だからこそ、しっかりチェックしておきたい!アフターメンテナンス

ローコスト住宅は資材の品質にはいくら問題ないとはいえ、年数が経てば、劣化や不具合はどうしても発生しやすくなります。
家づくりでは、そういった不具合にも対応できるサポートがあるかについても知っておくことも重要です。
とくにローコスト住宅は、コスト削減の工夫の一環で、メンテナンスが簡素化されている場合もあるため注意が必要です。
保障内容や適用期間など、しっかりと確認しておきましょう。
【チェックポイント】
| 定期点検のスケジュール | ・半年・1年・2年・5年・10年など、定期点検のタイミングは会社によって異なる。 ・一定の期間を過ぎると有償になる場合もあるため、無償点検はいつまでかも確認しておく。 |
| 保障内容の詳細 | ・構造躯体の保証はもちろん、雨漏り ・防水保証、シロアリ保証など、どれくらいの期間にどの保証がつくかを確認。 ・故障しやすいキッチンやお風呂などの住宅設備は、メーカー保証だけでなく、延長保証もあると安心。 |
| 不具合時の対応体制 | ・緊急時の連絡先や受付時間、土日も対応可能か |
| 長期保証の期間や適用条件 | ・法的に定められている「10年保証」に加えて、最長何年まで保証期間があるか。 ※住宅会社により「20年保証」「30年保証」「60年保証」などがある ・延長するための条件はあるか。 ※メーカーによっては定期点検を受けることや有償の補修工事を実施することが条件となっている場合がある |
まとめ
今回の記事では、ローコスト住宅も「20年後も安心して暮らせるのか」という不安を解消するために、「ローコスト住宅の価格が安い理由」や、「家の寿命を延ばす対策」「20年先を見越した家づくりのポイント」ついて解説しました。
国の建築基準をクリアしたローコスト住宅は、品質には問題なく、20年後でも安心して住めます。
しかし、家の耐久性や住み心地を維持していくには、地盤や構造の強さや、湿気や結露への対策、定期的なメンテナンスが求められます。
グッドリビングでは、「いい家を、より安く」を合言葉に、お客様にとってコストパフォーマンスの高い住まいを実現しています。
例えば、グッドリビングのどのプランも、「耐震・制震」を組み合わせた耐震性能や長期優良住宅基準を満たす断熱性能が標準仕様。高品質の家が、1,000万円台で建てられます。※建物の大きさや商品プランにもよります。
また、地域に精通したスタッフが土地探しからお手伝いし、アフターサービスは夜間も対応可能な年中無休の専用サポート窓口を設け、しっかり対応しています。
家づくりの無料相談会も行っていますので、お役立ち情報やグッドリビングの商品プランの詳細、モデルハウスのご予約など、お気軽にお問い合わせください。
▼ホームページはこちら▼