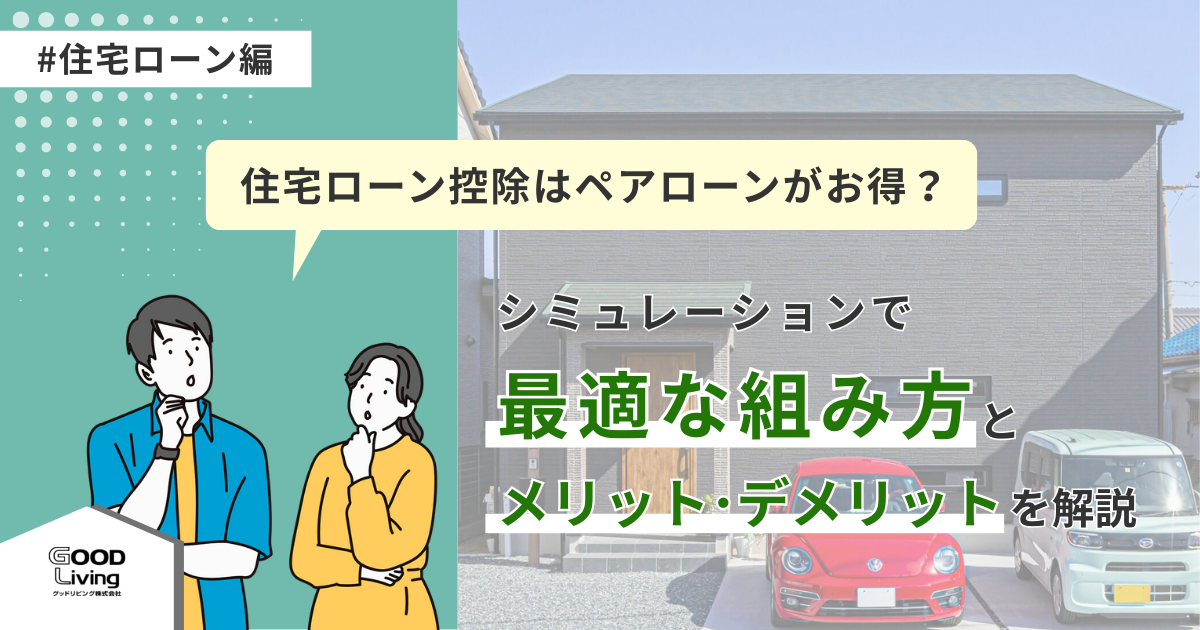COLUMN コラム
夫婦それぞれで住宅ローンを組むペアローン。
住宅ローン控除もそれぞれで利用できるため、控除額を最大限に利用できる可能性があります。
しかし、手続きの複雑さや将来的なリスクも伴うため悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ペアローンと住宅ローン控除の関係をシミュレーションを交えて解説。
どのようなケースでメリットが大きいのか、またどんなデメリットがあるのかも詳しくご紹介します。
ペアローンを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、支払った所得税や住民税の一部が還付・減税される制度です。ここでは住宅ローン控除について解説しますので、まずは控除の内容を知っておきましょう。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるためには、次のような適用条件を満たす必要があります。
| 適用条件 | 詳細 |
| 居住 | 住宅の新築・取得・増改築等の日から6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで引き続き居住していること |
| 収入 | 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること |
| 床面積 | 住宅の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上を自己の居住用として使用すること |
| 借入金 | 金融機関等からの返済期間が10年以上の借入金であること |
| 耐震基準 | 中古住宅の場合、1982年1月1日以降に建築された住宅であること |
また、住宅ローン控除では、基本的に「住宅ローンの年末残高の0.7%が13年間」に渡って控除されますが、住宅の種類によっては控除期間や限度額が異なる場合があります。
住宅の種類による控除上限や期間は次の通りです。
【一般の世帯】
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 年間最大控除額 | 控除総額 |
| 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅など) | 4,500万円 | 0.70% | 13年 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 0.70% | 13年 | 24.5万円 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.70% | 13年 | 21万円 | 273万円 |
| その他の住宅 | 0円 (2023年12月31日以前に建築確認を受けたものは2,000万円) | – (0.70%) | – (10年) | – (14万円) | – (140万円) |
さらに、子育て世帯や若者世帯になると上限金額が少し大きくなります。
子育て世帯・若者世帯とは、次のいずれかに該当する世帯のことです。
- 19歳未満の子を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
子育て世帯・若者世帯の住宅ローン控除額を具体的に次の表にまとめてみました。
【子育て・若者世帯】
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 年間最大控除額 | 控除総額 |
| 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅など) | 5,000万円 | 0.70% | 13年 | 35万円 | 455万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 0.70% | 13年 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 0.70% | 13年 | 28万円 | 364万円 |
従来は省エネ基準を満たさない住宅でも控除の対象でしたが、2024年以降どの世帯においても住宅ローン控除の対象となるのは、省エネ基準を満たした住宅のみとなりました。
要件が厳しくなったため、住宅を購入する際は注意が必要です。
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除を受けるための申請方法は、初年度と2年目以降で違ってきます。
それぞれの大まかな流れと主な必要書類は次の通りです。
【初めて申請する場合(1年目)】
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードなど)
- 住宅ローンの年末残高等証明書(借入先の金融機関から送付)
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
- 建物・土地の登記事項証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅の区分に応じた証明書類(長期優良住宅や省エネ基準適合住宅の場合)
住宅ローン控除を初めて受ける場合は、入居した翌年の2月中旬から3月中旬までに確定申告を行います。
申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンで簡単に作成でき、作成後は、e-Tax(ネットで提出)、郵送、または税務署の窓口で提出する方法から選ぶことになります。
【2年目以降】
- 住宅借入金等特別控除申告書
(初年度に確定申告をすると、10月〜11月頃に税務署から自宅に届く) - 年末残高等証明書
(住宅ローンを借りている金融機関から毎年10月〜11月ごろに届く)
会社員の場合、住宅ローン控除の2年目以降は確定申告をする必要はありません。
初年度に確定申告を済ませていれば、翌年からは勤務先の年末調整で自動的に控除を受けられるようになります。
年末調整で控除を受ける際には、税務署から届く「住宅ローン控除申告書」と、金融機関から届く「住宅ローンの年末残高証明書」を勤務先に提出するだけでOKです。
ペアローンでも住宅ローン控除は使える?
夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンでも、2人それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
ペアローンで住宅ローン控除を受ける場合、次のような条件を満たす必要があります。
- 2人とも住宅の持分を登記していること
- それぞれが住宅ローン控除を受ける要件を満たしていること
- 2人とも初年度の確定申告を済ませていること
ただし「共有名義+連帯保証」の場合は対象外となるため、あくまで2人が別々のローン契約をしている「ペアローン」である必要があります。
また、一方の所得が低くてそもそも税金を払っていない場合も、控除が受けられないので注意しましょう。
住宅ローン控除を最大にする負担割合をシミュレーション

ここでは、ペアローンで住宅ローンを組むことを前提として簡単なシミュレーションをしてみます。
【前提条件】
- 年収:夫600万円・妻300万円
- 住宅価格:5,000万円
- 長期優良住宅などの省エネ基準に該当する住宅
- 若者世帯
パターン1:各2,500万円ずつ借入(夫50%:妻50%)
| 夫 | 妻 | |
| 借入額 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 控除額(初年度) | 約17.5万円 | 約17.5万円 |
| 控除額(13年合計) | 約227万円 | 約227万円 |
⇒ 合計約454万円の控除が受けられる可能性あり!
パターン2:夫3000万円・妻2000万円の借入れ(夫60%:妻40%)
| 項目 | 夫 | 妻 |
| 借入額 | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 控除額(初年度) | 約17.5万円 | 約17.5万円 |
| 控除額(13年合計) | 約260万円 | 約182万円 |
⇒ 合計約442万円の控除が受けられる可能性あり!
パターン3:夫3,500万円・妻1,500万円の借入れ(夫70%:妻30%)
| 項目 | 夫 | 妻 |
| 借入額 | 3,500万円 | 1,500万円 |
| 控除額(初年度) | 約17.5万円 | 約17.5万円 |
| 控除額(13年合計) | 約260万円 | 約136.5万円 |
⇒ 合計約396.5万円の控除が受けられる可能性あり!
パターン4:夫4,000万円・妻1,000万円の借入れ(夫80%:妻20%)
| 項目 | 夫 | 妻 |
| 借入額 | 4,000万円 | 1,000万円 |
| 控除額(初年度) | 約17.5万円 | 約17.5万円 |
| 控除額(13年合計) | 約260万円 | 約91万円 |
⇒ 合計約351万円の控除が受けられる可能性あり!
夫600万円・妻300万円で5,000万円の省エネ住宅をペアローンで購入する場合、夫婦50:50のローン負担がもっとも控除額の合計(約455万円)をフルに活用できて理想的です。
ただし、妻の年収が300万円で2,500万円を借りるのはやや負担が重めになる可能性もあるため、夫60%・妻40%の方が年収とのバランスが現実的で安心感があるでしょう。
今後の働き方や出産・育休・転職などライフプランなども踏まえて、「控除額」だけでなく「無理のない返済プラン」で決めるのがベストです。
ペアローンと単独ローンの控除額を比較シミュレーション

それでは、夫単独ローンとペアローンの場合では、控除額にどれくらいの違いが出てくるのでしょうか?
ここでは、単独ローンとペアローンの控除額を比較シミュレーションしてみます。
【前提条件】
- 年収:夫800万円・妻300万円
- 住宅価格:5,000万円
- 長期優良住宅などの省エネ基準に該当する住宅
- 若者世帯
| 項目 | 夫単独ローン | ペアローン |
| ローン借入額 | 5,000万円 | 夫:2,500万円 妻:2,500万円 |
| 年間控除額(目安) | 約17.5万円 | 夫:約17.5万円 妻:約17.5万円 |
| 控除額(13年合計) | 約260万円 | 夫:約227.5万円 妻:約227.5万円 |
| 控除合計 | 約260万円 | 約455万円 |
夫単独ローンでは年収により控除額の上限が約260万円にとどまる一方、ペアローンであれば夫・妻それぞれが控除を受けられるため、合計約455万円の控除が可能に。
同じ条件でも、ペアローンの方が約195万円多くお得という結果になります。
ただし、産休・育休などどちらかの収入が減れば、住宅ローン控除が一時的に使えなくなる可能性があるという点に注意が必要です。
そのため、将来的に育休や時短勤務、退職などを想定している場合は最初から夫のローン負担割合を多めに設定しておくと、控除の無駄を防ぎやすくなるでしょう。
住宅ローンは長期の契約になるため、収入状況の変化も見越した設計が大切です。
共働き夫婦がペアローンを選ぶ理由とは?|メリットとデメリット

住宅ローン控除においてペアローンは大きなメリットがありますが、メリットとデメリットどちらも理解した上で検討が必要です。ここでは、ペアローンのメリットとデメリットを紹介しますので確認してみてください。
ペアローンのメリット
ペアローンのメリットとしては、次のようなものがあります。
- 夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる
- 年収に応じて返済負担を調整しやすい
- 団体信用生命保険(団信)にそれぞれ加入できる
- 借入可能額が増やせる
ペアローン最大のメリットは、やはり住宅ローン控除を2人分使えること。
夫婦それぞれがローン契約をしていれば、1人で組むよりも控除枠が2倍になり節税効果も大きくなります。
また、意外と大きいのが団体信用生命保険(団信)を2人それぞれでかけられること。
もしどちらかに万が一のことがあっても持ち分のローンは完済になるので、残された家族の生活への影響を減らせます。
共働きでしっかり収入がある夫婦には、ペアローンは金銭面・安全面の両方で大きなメリットが得られると言えるでしょう。
ペアローンのデメリット
ペアローンのデメリットとしては、次のようなものがあります。
- 登録免許税や司法書士費用などの諸費用も2人分かかる
- 離婚や片方がローン返済できなくなったときの処理が複雑
- 育休や退職で収入が減ると控除が受けられない可能性がある
- 単独ローンと比べて柔軟な借り換えがしにくい
住宅ローンの契約が2人分必要になるので、書類も審査も全部2回ずつ。
登記や司法書士への費用、保証料などの初期費用も2人分になるので、地味に出費がかさみます。
また、何より気になるのが、離婚や一方の収入減など「予定外のこと」が起きたときの複雑さ。どちらかが仕事を辞めた場合、一人分の控除が使えなくなることもあるでしょう。
ペアローンはうまく使えばかなりお得ですが、「ずっと共働きが続く」ことが前提の制度でもあります。
育休・転職・離婚など…将来のライフプランに少しでも不安があるなら、単独ローンのほうが気楽ではあるでしょう。
収入合算との違い
収入合算とは、夫婦や親子など複数人の収入を合わせて、住宅ローンの審査を受ける方法のこと。
夫の年収だけでは借入額が希望に届かない場合に、妻の収入も合算して「世帯年収」として審査してもらうことで、より多くの金額を借りられる可能性のある制度です。
ペアローンと似ていますが、比べてみると次のように違いが出てきます。
| 比較項目 | 収入合算(連帯保証型) | 収入合算(連帯債務型) | ペアローン |
| ローン契約者 | 主債務者のみ(保証人が加わる) | 主債務者+連帯債務者 | 夫婦それぞれが契約者(別々に2本) |
| 審査に使う収入 | 2人分 | 2人分 | 2人分 |
| 住宅ローン控除の対象 | 主債務者のみ | 主債務者のみ (一部の金融機関では、連帯債務者が住宅ローン控除を受けられるケースあり) | 2人とも対象 |
| 団信の対象 | 主債務者のみ | 主債務者のみ (金融機関によって連帯債務者が入れる場合もある) | 夫婦それぞれ加入できる |
| 名義と持分 | 主債務者 | 柔軟に設定できる | 負担と持分を一致させて分ける |
収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」の2つがあります。
「連帯保証型」では、配偶者の収入を借入審査に使うことはできますが、実際にローンを返済するのは主債務者のみ。
住宅ローン控除や団信の対象になるのも主債務者だけなので、控除は1人分しか受けられません。
一方「連帯債務型」は、夫婦が一緒にローン契約を結び、共同で返済していくスタイルです。
名義や持分を柔軟に設定できるメリットはありますが、基本的には控除を受けられるのは主債務者のみ。
ただ、一部の例外では連帯債務者が控除を受けられる場合も。
対して「ペアローン」は、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを契約する形です。
住宅ローン控除や団信も2人分利用できるため、万が一のときのリスク分散にも繋がるでしょう。
年収の何倍まで組めるのかについて以下のコラムも参考にしてください。
▶︎住宅ローンは年収の何倍まで組める?借入可能額の目安を徹底解説
ペアローンの住宅ローン控除を最大限活用するときの注意点

最後に、ペアローンを組んだ際に気になることについて注意点をご紹介します。
夫婦のどちらかの所得が減ると控除額が減る可能性がある
ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられますが、控除額は「その年に払った税金の範囲内」でしか適用されません。
そのため、どちらかの収入が減ると、本来の控除額を満額受けられなくなる可能性があります。
具体例を挙げると、妻が産休・育休に入り、一時的に収入がゼロになった場合です。
収入がなくなると所得税や住民税も発生しないため、その年は妻の住宅ローン控除を受けることができなくなります。
夫の分の控除は通常どおり適用されますが、妻の控除枠は使えずに税額控除が失われてしまうことに。
一時的に収入が無くなるリスクを考えるなら、最初から夫のローン負担割合を多めに設定するのも一つの方法です。
住宅ローン控除の上限を超えないようにする工夫が必要
住宅ローン控除には上限があるため、借入額が多すぎると控除枠を使い切れない可能性があります。
たとえば、省エネ基準を満たした住宅の場合、控除の対象となるローン残高の上限は1人あたり4,000万円。
長期優良住宅なら、1人あたり5,000万円まで控除を受けることができます。
もし、夫が6,000万円、妻が2,000万円のローンを組んだ場合、夫の控除は上限の5,000万円です。
超えた1,000万円分には控除が適用されないので、上限を超えないようにライフプランと合わせて2人の借入額を調整しましょう。
夫婦のどちらかが働けなくなった場合のリスク
ペアローンは、どちらかが働けなくなると、一人分の収入だけでローンの返済を続けなければならなくないリスクが大きいと言えます。
たとえば、病気・ケガ・リストラなどで収入が減った場合、本来2人で分担するはずだったローンの負担が大きくのしかかることに。
ギリギリの返済計画を立てていれば、家計が一気に苦しくなる可能性は高いです。
リスクを考えるとペアローンを組む際には、どちらかが働けなくなったときの返済計画もよくシミュレーションしておきましょう。
離婚時のローン問題
住宅ローンは、たとえ離婚しても支払い義務はそのまま残ります。
家を売ってローンを完済できれば問題ありませんが、売却価格がローン残高を下回る場合、残った借金をどう分担するかを決める必要が出てくるでしょう。
また、一方が家に住み続ける場合でも、片方だけのローン契約を解除するのは難しいため、どちらかがローンを引き継ぐか、借り換えを検討する必要があります。
離婚時には特にローン問題が複雑になることが多いです。
ペアローンを組む際には「もしものとき」にどうするかを事前に話し合い、無理のない借入額や契約内容を決めておきましょう。
まとめ|住宅ローンの活用はグッドリビングが得意としています!
今回は、ペアローンの場合の住宅ローン控除について解説しました。
ペアローンをうまく活用すれば、住宅ローン控除を最大限利用してかなりの節税効果が得られます。
夫婦や家族と話し合い、将来のライフプランを含めて、納得のいく割合で住宅ローンの負担を決めてみてください。
当グッドリビングでも住宅ローンの無料相談を受け付けています。
ローン審査通過の多数実績もありますので、ペアローンや収入合算の詳しいお話をお求めの方はぜひ下記ホームページよりご相談ください!
▼ホームページはこちら▼