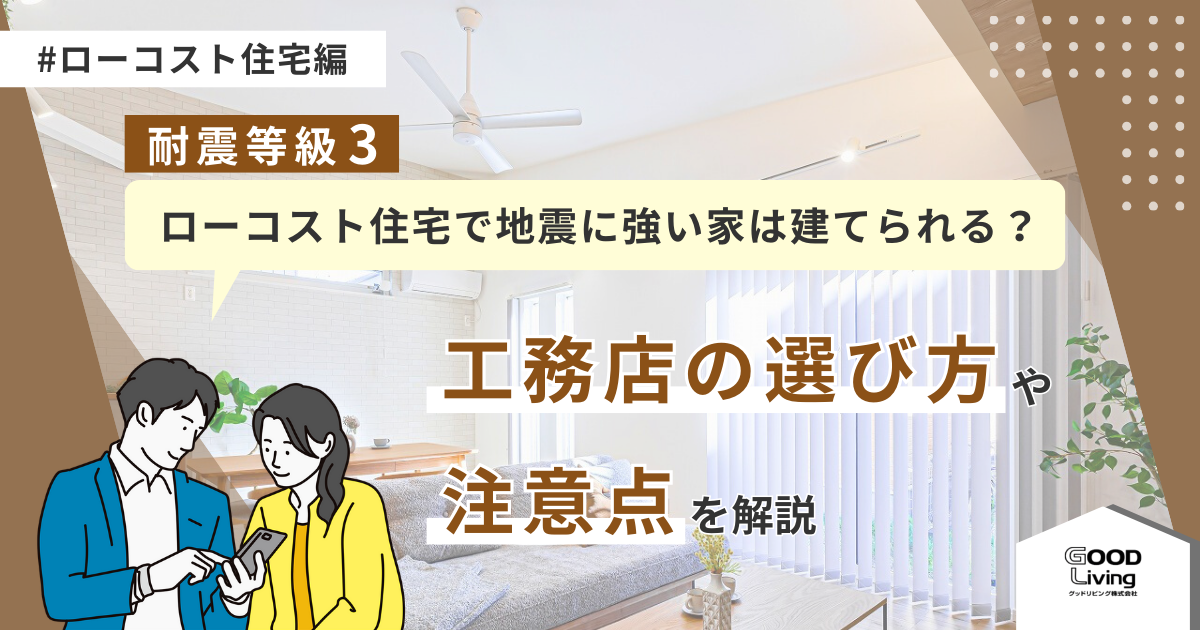COLUMN コラム
「ローコストで家を建てたいけど、耐震性が心配」「地震に強い家が建てられる会社ってどうやって見分ければいいの?」
できるだけコストを抑えて希望の間取りを形にするなら、ローコストの注文住宅がありますが、耐震性など性能に問題がないかと不安になりますよね。
そんなお悩みを持つ人に向けて今回の記事は、最も耐震性の高い耐震等級3の基準や地震に強い家が建てられる会社の選び方について解説。
また、ローコスト住宅を選ぶ際の注意点についても詳しく解説します。不安が解消できれば、理想の家づくりをスタートできますよ。
耐震等級3の住宅を選ぶ理由

耐震等級は住宅の地震に対する強さを示す重要な指標です。柱や梁(はり)、主要な壁、基礎部分などの強さを評価し、どの程度の地震なら倒壊しないかを等級で示します。等級1から3まであり、等級3が最も高い耐震性能を表します。
耐震等級3の基準
耐震等級3は、数百年に一度発生するような大規模地震に対しても、建物の安全性を確保できる最高レベルの耐震基準です。
耐震等級3の認定には、構造強度や耐力壁の配置、基礎構造の安定性、接合部の強度で基準を満たす必要があります。
この等級の建物は、大地震が発生した後でも、軽微な修繕で継続して住み続けることが可能です。
日本では、南海トラフ地震のような大規模地震の発生が予測されていることから、住宅の耐震性能は特に重視されています。
近年では、長期にわたり良好な状態で使用できる優れた住宅として国が認定する「長期優良住宅」の基準も見直されており、2022年(令和4年)からは耐震等級3のみが対象となっています。
耐震等級3のメリット
耐震等級3の住宅を建てると、大地震に見舞われた際にも高い安全性が確保され、大切な家族の命と財産を守ることができるほか、経済面でもさまざまな優遇措置があります。
例えば、耐震等級の高い建物は地震による被害が少ないと判断され、地震保険料が最大50%割引される場合があります。
また、建物の長期的な安全性が評価され、住宅ローンで金利の優遇を受けられることも。
さらに、将来住宅を売却する際には、資産価値の維持にもつながります。
地震に強いローコスト住宅の特徴

一般的に「ローコスト住宅の耐震性は十分なのか」という懸念がありますが、ローコストでも耐震等級3を満たす住宅を建てることは可能です。ただし、多くの住宅メーカーでは、基本プランをベースに、オプションとして耐震性を向上させるための選択肢を用意しています。例えば、壁や柱の強度を上げたり、地盤の補強工事を行ったりすることで、必要な耐震性能を確保できます。
耐震等級は耐震性を判断する指標の一つですが、地震に強い家の特徴として、さらに以下のポイントにも注目しておくと安心です。
耐久性を考慮した建材を使用している
住宅の寿命に大きな影響を与えるものとして、建材の品質があります。
特に住宅の主要構造部分には、長期間の使用に耐えられる高品質な建材を使用することが重要です。
日本の気候は高温多湿で、季節の変化も大きいため、そのような気候で育った国産木材は最適です。
さらに、国産木材は耐久性に優れているだけでなく、地域の気候に自然に適応しており、湿度の変化にも対応しやすいという特徴があります。
制震・免震工法の活用している
従来は、建物の壁を強化し、揺れに耐える「耐震構造」が主流でした。
しかし、2016年に発生した熊本地震では、大きな揺れが何度も続いたことで、複数回の揺れによって建物の損傷が段階的に進行する問題が浮き彫りとなりました。そのため、最近では「制震」と「免震」が注目を集めています。
制震工法は、制震ダンパーを用いた方法で、地震のエネルギーを吸収し、建物の揺れを抑制する仕組みです。地震の力を建物に伝わりにくくし、建物自体へのダメージを軽減できます。
一方、免震工法は、建物と地面の間に特殊な装置を設置し、地震の揺れを受け流す方法です。地震のエネルギーが建物に直接伝わるのを防ぎ、建物全体の揺れを大幅に低減させることが可能です。
| 耐震技術 | 建物を頑丈にして揺れに耐える |
| 制震技術 | 制震ダンパーで地震のエネルギーを吸収して揺れを抑える |
| 免震技術 | 建物と地面の間に特殊な装置を設置して揺れを受け流す |
制震技術も免震技術も導入には相応のコストがかかるため、ローコスト住宅の場合、対応できないケースも考えられます。
しかし、地震大国である日本において、導入を検討する価値は十分にあります。
特に地震の多い地域や、より高い安全性を求める場合には、積極的な検討をしてみましょう。
ローコスト住宅の注意点

ローコスト住宅を選ぶ際には、耐震性が十分に確保されているかも重要ですが、長期的な視点で満足できる家づくりを意識しておくことも大切。ここではローコスト住宅で後悔されやすい点を3つ紹介します。
設備や間取りの自由度が低い
ローコスト住宅は、建材やデザインを標準化して量産することでコストを抑えているため、個別の要望に応じた変更には制限が生じます。
注文住宅の場合でも、間取りの自由度には限界があり、希望通りにならないことがあるため、将来の生活に不便を感じる可能性があります。
特に、吹き抜けやスキップフロアなど、施工が複雑になる設計は、コストや工期の関係で対象外となることが多いです。
また、住宅設備についても、あらかじめパッケージ化された選択肢の中から選ぶ形となり、細かな要望や特別なこだわりを反映させることが難しい場合があります。
そのため、ローコスト住宅を検討する際は、これらの制約を十分に理解した上で、自分のライフスタイルに合わせた選択をすることが重要です。
住宅の寿命が短い
住宅の寿命は、施工の品質によって大きく左右されます。職人の技術力が不十分な場合や手抜き工事が行われた場合、建物の耐久性は著しく低下することになります。
例えば、断熱材の施工では、隙間や圧縮などの不具合がないことが求められるため、職人の技術が必要です。
もし、適切な施工が行われていなかった場合、結露を引き起こし、構造材の腐食やカビの発生につながる可能性があります。
特に木造住宅は湿気や雨水には注意しなければなりません。
断熱材の施工だけでなく、窓まわりや屋根、外壁の防水処理が適切に行われていないと、建物内部への水が侵入して構造材の劣化を招き、住宅の寿命を大幅に縮めることになります。
価格と性能のバランス
近年の住宅市場は、新型コロナウイルスの影響で建築資材の価格が高騰し、住宅全体の価格も上昇傾向にあります。
さらに人手不足による人件費の上昇も重なり、ローコスト住宅でも建築費用の高騰は避けられない状況となっています。
このような状況では、単に価格の安さだけで住宅を選ぶことは賢明ではありません。
建材の品質が低かったり、施工技術が不十分だったりすると、将来的に予想以上のメンテナンス費用が発生する可能性もあります。
長期的な視点で考えるなら、適切な耐震性能や住宅の基本性能を確保することは必須です。
初期費用が多少高くなったとしても、長期的な維持費用や安全性を考慮し、価格と性能のバランスを重視した選択が大切です。
地震に強いローコスト住宅会社を選ぶ際にチェックしておきたい4つの対策

ローコスト住宅の購入では、施工会社の選定が成功の鍵となります。しっかりと情報 収集を行うことで「こんなはずではなかった」と後悔することも防げます。ここでは会社選びで押さえておきたい4つの対策を紹介します。
モデルハウスを見学する
ローコスト住宅を建てる際の会社選びで、まずおすすめなのがモデルハウスの見学です。
実際の空間を訪れることで、カタログやウェブサイトだけでは分からない建材や設備の質感を直接確認できます。
また、間取りの使い勝手はもちろん、採光や通風といった実際の住み心地も体感できるため、より具体的なイメージを掴むことができるでしょう。
さらに、施工の細部や仕上げの品質を実際に確認できることも大きなメリットとなります。
また、モデルハウス見学時に担当者と直接対話することで、会社の対応力や信頼性が実際に判断でき、長期的なパートナーとして相応しい会社かどうかを見極めることも可能です。
アフターメンテナンスサービスの内容を確認する
住宅の主要な部分には、それぞれ耐用年数があります。
例えば、外壁や屋根は20〜30年、水回りの設備は10〜20年程度が一般的な目安です。
これらの耐用年数を最大限に活かし、できるだけ長く快適に住み続けるためには定期的なメンテナンスが欠かせません。
そのため、住宅会社を選ぶ際にはアフターサービスの充実度をしっかりと確認することが重要です。
特に、長期保証制度の有無や保証内容はしっかりとチェックしましょう。
充実した保証制度があれば、将来的な修繕やメンテナンスの際にも安心でき、住宅を長く快適に使い続けることが可能です。
断熱性など性能もチェックする
住宅の断熱性能は、快適な暮らしを実現する上で欠かせません。
室内の温度を年間を通して適切に保ち、冷暖房費を抑えるためには、高気密・高断熱住宅の建築実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。
断熱性能を客観的に評価する際には、いくつかの指標が参考になります。
例えば、熱損失係数を示す「Q値」、外皮平均熱貫流率を表す「Ua値」、気密性能を示す「C値」、さらに*住宅の断熱性能を総合的に評価する「断熱等性能等級」などです。
これらの数値をチェックすることで、その住宅がどの程度の断熱性能を備えているのか、具体的に判断することができます。
技術に定評があるか確認する
ローコスト住宅では、さまざまな工夫によってコストを削減しています。
実績のあるハウスメーカーや工務店は、建設コストを抑えるために建物の品質や安全性を損なうようなことはしません。
建材の一括仕入れや施工の効率化など、自社独自の工夫が見られる会社を選びましょう。
また、長く快適に住み続けられる家を建てるためには、確かな技術力と信頼できる施工品質を持つ会社を選ぶことが不可欠です。
価格の安さだけで判断するのではなく、会社の実績や技術力をしっかりと確認することで、長期的に満足できる家づくりが可能になります。
まとめ
今回の記事では、ローコスト住宅で耐震面に不安のある人向けに、耐震等級3の基準や、地震に強いローコスト住宅の特徴、信頼できる会社の選び方について解説しました。
快適で安全な暮らしを長く続けるためには、価格だけでなく住宅の性能とのバランスを考慮することが大切です。
グッドリビングは、いち早くローコスト住宅を手掛けた、創業45年の歴史と15,000棟を超える施工実績を誇る会社です。
高気密・高断熱住宅の施工に優れ、長期優良住宅基準と同等の省エネ性能を実現。
さらに、制震技術を標準仕様として採用し、高い耐震性能も確保しています。
また、吹き抜けなどの自由度の高い設計にも対応し、追加費用の心配なく理想の住まいを叶えられる「定額制の注文住宅プラン」も提供しています。
モデルハウスでは、見学会を定期的に実施しているほか、無料相談も実施しています。
見学会の予約や家づくりについて気になることがございましたら、お気軽に問合せください。